「果敢にチャレンジする企業を応援」
■経済産業省製造産業局 産業機械課長 玉井優子
平成31年の新春を迎え、謹んでお慶びを申し上げます。
我が国経済は、安倍政権発足から6年での様々な改革や金融・財政政策によって名目GDPは54兆円増加、正社員の有効求人倍率は1倍を超え、2%程度の高水準の賃上げが5年連続で実現するなど、着実に成長軌道に乗りつつあります。
こうした中、ロボットやAI、IoT技術の登場により、新たな付加価値や製品・サービスが生まれるなど、企業を取り巻く競争環境は劇的に変化しています。
第4次産業革命時代に、日本が勝ち残り、世界をリードしていくためには、様々な業種や企業、人、機械、データなどが繋がる「Connected Industries」の実現が重要な鍵となります。このコンセプトは、データを介して、様々な繋がりが生まれることで、新たな産業や付加価値の創出、社会課題の解決につなげていくものです。日本の強みはものづくりの現場にある、と言われますが、日本の製造業は深刻な人手不足に直面しています。こうした現場に、ロボットやAI、IoTなどの技術を導入することで、人材育成や技能の伝承などを実現していく必要があります。
また、アジアを中心とする新興国の成長を取り込み、日本の優れた技術を世界に展開していくことも重要な課題です。そのため、最先端のインフラシステム輸出や国内外の企業の連携等による海外展開を後押しすべく、関係部署とも連携しながら、海外進出のための環境整備等を積極的に実施してまいります。
こうした取組に加え、中小企業の取引条件を改善し、サプライチェーン全体で付加価値を生み出す取組も不可欠です。産業機械業界では、業種別の自主行動計画が策定され、着実に取引適正化の取組が進んできています。発注側、受注側双方の理解、協力を進め、企業間取引が『Win-Win』の関係となるよう、引き続き、下請取引適正化を産業界全体で進めて頂きたいと思います。
福島の復興は、経済産業省の最重要課題です。経済産業省では、福島県とともに、「福島イノベーション・コースト構想」の中核となるロボットテストフィールドの整備等に取り組んでいます。ロボットテストフィールドは、試験飛行や実証実験を行える場です。来年3月に全面開所予定であり、ワールドロボットサミット2020も開催予定です。産学官の関係者に広く活用いただきたいと思います。
本年10月には消費税率引き上げが予定されており、増税後の反動減も懸念されているところですが、こうした影響によって景気の腰折れやデフレ脱却に向けたチャンスを逃してはなりません。そのため、経済産業省では各種支援策を通じて、国内景気の下支えや、果敢にチャレンジする企業を応援してまいります。
これからも皆様の現場の生の声をお伺いし、それを産業政策に生かしていきたいと考えております。何かお困りごとやご提案などがございましたら、どうぞお気軽にお声を掛けてください。
最後になりましたが、本年は、新しい元号がスタートする節目の年でございます。本年が、皆様方にとって更なる飛躍の1年となりますよう祈念いたしまして、新年の挨拶とさせていただきます。
「2019年は新しい時代の幕開け」
■日本産業機械工業会 会長 斎藤 保
![190101年頭1-1 190101年頭1-1]() 2019年を迎えるに当たり、新年のご挨拶を申し上げます。
2019年を迎えるに当たり、新年のご挨拶を申し上げます。
皆様には、気分も新たに新年を迎えられたことと思います。
昨年を振り返りますと、国内では西日本豪雨や台風21号、北海道胆振東部地震等の自然災害による被害が相次ぎました。そうした中、2025年の国際博覧会(万博)の大阪・関西開催が決定したことは、自然災害が続いたわが国に明るい話題をもたらしました。なお、経済面では、国内総生産(GDP)7~9月期が2期ぶりに落ち込むなど、足元では減速傾向がみられました。
一方、海外については、米中貿易摩擦や新興国・資源国経済の動向、英国のEU離脱交渉の展開などリスク要因が多岐に亘っており、世界経済の先行き不透明感が高まりました。
他方、私ども日本産業機械工業会にとっては、創立70周年の記念すべき年でもありました。2018年度上半期の受注額は2兆4,131億円、前年同期比102.2%と2年連続で前年を上回り、海外が中国向けの減少で横ばいとなったものの、国内の製造業・非製造業向けが増加するなど、内需が堅調に推移しました。
2019年は、天皇陛下がご退位され、皇太子殿下がご即位される新しい時代が始まろうとしております。
日本経済においては、「いざなぎ景気」を超えた現在の景気回復をさらに力強いものとしていくための非常に重要な一年であり、激動する国際経済の状況に左右されない成長力を獲得するため、グローバリゼーションの展開とイノベーションの加速により、あらゆる産業の生産性をさらに高めていく必要があると考えます。
我々産業機械業界としては、TPP11や日・EU経済連携協定による自由貿易圏の拡大を追い風にグローバル展開を加速するとともに、第4次産業革命などの新たなデジタル化の波を取り込み、関連産業と連携しながら、他国をしのぐ高付加価値製品・サービスを追求するなど、さらなる技術革新で世界のニーズに応えていきたいと思います。
また、社会インフラの老朽化対策に資する新技術・システムを創出し、国土強靱化、防災・減災に向けて積極的に貢献していきます。
併せて、会員企業の持つエネルギー・環境分野の革新技術により、地球温暖化や廃棄物削減を始めとする地球規模での環境対策にも積極的に取り組んでいきます。
政府におかれましては、生産性向上に向けた設備投資の促進や技術開発、IoT人材の育成等を下支えする各種支援の充実などに加え、経済連携の推進や日米の物品貿易協定(TAG)交渉などの通商戦略に、引き続き取り組んでいただきたいと思います。また、消費税率の引き上げへの対策については、着実な景気対策の実施をお願いいたします。
さらに、外国人労働者の受入制度の整備については、深刻な人手不足で悩む産業にとって朗報であり、産業競争力を高めていく観点からも、わが国にとって良い制度となるよう環境整備を進めていただきたいと思います。
また、昨年12月に開催されたCOP24(第24回国連枠組み条約締約国会議)が「パリ協定」の実施指針を採決したことで、地球温暖化対策の枠組みが2020年から動き出すことになりましたが、日本の削減目標を達成するために、原子力発電を含めた「安定供給、経済効率性、環境適合、安全性(3E+S)」を考慮した最適なエネルギーミックスの実現に向けた取り組みを加速していただきたいと思います。
年頭にあたり考えるところを述べさせていただきましたが、関係各位におかれましては一層のご指導、ご協力をお願いしますとともに、皆様のご多幸を心からお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。
「引き続き高水準を期待」
■日本工作機械工業会 会長 飯村幸生
![190101年頭1-2 190101年頭1-2]() 2019年の新春を迎え、謹んで新年のお慶びを申し上げます。
2019年の新春を迎え、謹んで新年のお慶びを申し上げます。
昨年2018年を振り返りますと、世界では保護貿易的な気運の高まりや地政学的リスク等もみられましたが、我が国工作機械業界の受注は、年初来内外需ともに総じて高水準となりました。内需では半導体産業や自動車産業の投資が好調に推移して、幅広い産業で需要が盛り上がりました。外需では、中国が電気機械のみならず年央以降一般機械や自動車等で設備投資に減速感が漂い始めましたが、欧州、北米は堅調に推移しました。この結果、2018年の受注総額は2年連続史上最高額を更新しており、1兆8,000億円台に達したと見込まれます。
国際政治・社会情勢等、外部的リスク要因は内在していますが、本年も基調的には受注は引き続き高水準が持続していくことが期待されます。関係業界の皆様には引き続き円滑な部品供給を始めとするご支援をお願い致します。
このような受注環境にあって、世界の工作機械産業は大きな技術的・社会的変革期への対応を求められております。我が国の “Connected Industries” を始め、ドイツの “Industrie 4.0”、アメリカの “Industrial Internet”、中国の “中国製造2025”、等、IoTを活用したスマート・マニュファクチャリング技術、AI(人工知能)技術、三次元積層造形技術等、次世代における付加価値創造に向けた取り組みが競われています。また、少子高齢化時代に適応した工場設備の高度な自動化技術、自動車の電動化の進展、航空機産業の成長に伴う難削材需要の増加等、工作機械産業は多様化するユーザーニーズに対応した製品作りが求められております。
日本の工作機械業界は、世界のものづくりをリードすべく、製品の高付加価値化やユーザーニーズの多様化に的確に対応した取り組みを進めております。昨年11月に開催したJIMTOF・Tokyo 2018では過去最高となる15.3万人の来場者をお迎えして、工作機械分野における世界最先端のIoT、自動化、積層造形等の技術・製品を世界に向けて発信しユーザーの皆様に提案させて頂きました。併せて、全国から学生を招待する「工作機械トップセミナー」開催のほか、企画展示や工作機械検定の実施を通じて、工作機械産業の社会一般に対するプレゼンス向上も図りました。
日工会は、本年につきましても、産学官連携の強化、標準化戦略の強化、JIMTOFの求心力の強化、人材確保・周知策の強化等、業界に共通する課題への取り組みを推進して参ります。
関係各位には当工業会の事業に対する一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。
本年が皆様にとって更なる飛躍の年となることを祈念致しまして、年頭のご挨拶とさせて頂きます。
「生産額5,000億円超えを期待」
■日本機械工具工業会 会長 牛島 望
![190101年頭1-3 190101年頭1-3]() 新年明けましておめでとうございます。謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
新年明けましておめでとうございます。謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
昨年も実に多事な1年ではありましたが、ビジネスは前年に引き続き拡大基調を維持することができたのではないかと思います。暦年ベースで見ると、1月から10月までの工具出荷額は4,347億円と、17年の同時期との比較では9.7%の伸びとなり、内需、外需双方で大きく伸長させることができました。但し、工作機械やロボットの受注の伸びに陰りが出ており、足下では不透明感が増していますが、本年3月までの年度通年で、宿願であった生産額5,000億円超えを是非達成したいと念じるばかりです。
一方では、世界の情勢は全く予断を許しません。トランプ大統領のイニシアテイブによる米中貿易戦争の影響が我々の工具ビジネスにも影響してくる事態は、1年前には予想すらできなかったことです。中国製の超硬合金素材に対して、米国は25%もの関税をかける対象に指定しています。米国に輸出している中国メーカーも困るでしょうが、素材を輸入して完成品に加工している米国メーカーも困惑しているに違いありません。
どのような物品でも関税を大幅に上げればこのような双方痛み分けの事態になることは米国当局としても当然覚悟の上でしょうから、今回の貿易戦争は米国の本気度を示し、長期にわたり高関税政策が継続される可能性が高いと考えます。また、中国の一部ハイテクメーカーとの取引制限を日本等の第三国にも要求してくる事態にも驚かされます。中国の主要国策の一つである、「中国製造2025」を意識した動きであり、米国は中国の強大化を真剣に懸念し始めているのではないかと思わざるを得ません。
もう1つは天災です。最近の地震の多さ、夏から秋にかけて次から次へと襲来した台風と、昨年は6月18日の大阪北部地震以降、毎週のように地震か台風が発生したのには参りました。私の所管する事業部門でも岡山県高梁市に所在する焼結部品工場の従業員のうち、60名程が床上浸水の被害を受け、北海道奈井江町に所在する刃先交換チップ工場は北海道胆振東部地震に伴う停電で3日間の操業ストップ、関西空港の台風による冠水の影響で物流混乱と対応に追われ、BCPの重要性を改めて感じる一年でした。日本で生活していく以上、このような天災との付き合いは避けて通れないと諦めるしか無いのですが、企業は、地震に遭っては火を出さないことが最も重要です。個人は、地震でも台風でも飲料水を確保することが最優先です。10リットル入りポリタンクを自宅に常備しておくことをお勧めします。
最後になりますが、関西企業に籍を置く身としては、1970年以来、55年ぶりの万博を大阪に招致できたことは大変嬉しいことです。関西経済連合会会長を務める弊社・住友電工会長の松本も、世耕経済産業大臣や松井大阪府知事、吉村大阪市長と一緒にパリに赴き、11月23日の投票日直前まで各国へ日本支持を訴えかけました。本人帰国後の弁では、今回、他の候補国に大差をつけて日本・大阪が選ばれたのは、日本人の勤勉さや高い倫理観が各国から信頼されているからこその結果だと痛感したとのことでした。日本・日本人に任せておけば確実にやり遂げるだろうとの安心感を世界中の皆様に持って頂いているということなのでしょう。
本年も宜しくお願い申し上げます。
「ビジネスチャンスは拡大している」
■日本工作機器工業会 会長 寺町 彰博
![190101年頭1-4 190101年頭1-4]() あけましておめでとうございます。
あけましておめでとうございます。
年頭に際し、所見を述べさせていただきます。
昨年の世界経済は、消費者や企業の良好なマインドを背景に好調なスタートを切りました。しかしながら、米国と各国間における経済摩擦や英国のEU離脱協議の難航など、保護主義やポピュリズムの動きが見られる中、先行きに対する不透明感が高まりました。
日本に目を向けますと、地震、猛暑、豪雨や台風などの自然災害の影響や世界経済の不安定化により、好調に推移していた輸出や生産も弱含んでまいりました。一方で、2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催に引き続き、2025年の国際博覧会の開催地が大阪に決まり、将来に向けた夢や希望がもたらされた年でもありました。
世界経済の先行きに対する不透明感が高まる中、自動車の電動化と自動運転化に加え、AI、IoTなどの高度情報技術による繋がりやロボットを活用した仕組みが進展し、私たちのビジネスチャンスは拡大しています。一方で、そのような高度情報技術を武器として、巨大なプラットフォーマーが様々な市場を凄まじいスピードで席巻するようになり、日本においても従来の系列や競合関係にとらわれない企業連携が相次ぐなど、これまででは考えられなかった変革を迫られています。このように業界の垣根を越えて連携することにも臆すること無く、製品やサービスの付加価値を高めていかなくては、生き残りが厳しい時代へと移行しているのかもしれません。
そのような中、私たちに求められていることは、変化を恐れず、ダイナミックなイノベーションを大胆なスピードをもって成し遂げていくこと、そして自動化が進展していく中で私たちの強みとしている高品質・高付加価値な製品群に更なる磨きをかけていくこと、この2点ではないでしょうか。
これらを両立できれば、必ずや私たちはグローバル競争の中で打ち勝ち、世界の製造業を引き続き牽引していくことができるものと考えております。従いまして、当工業会といたしましても、会員の皆様と強い信念を共有するとともに、これまで以上に連携を深め、日本の製造業の発展に寄与できますよう、積極的な活動を展開してまいる所存です。
最後になりましたが、会員企業様の益々のご発展と皆様のご健勝とご多幸を心より祈念し、年頭の挨拶とさせていただきます。
.jpg) 新年明けましておめでとうございます。
新年明けましておめでとうございます。.jpg) 2019年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。
2019年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。.jpg) あけましておめでとうございます。
あけましておめでとうございます。
.jpg)



_0.jpg)
.jpg)
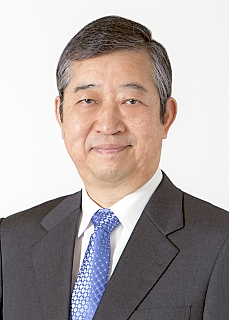


.jpg)
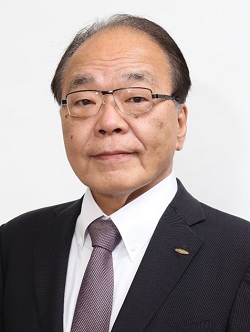

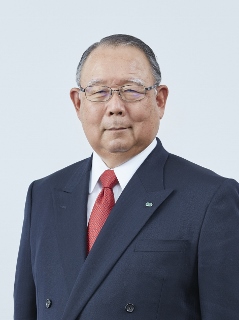

.jpg)




.jpg)
.jpg)




